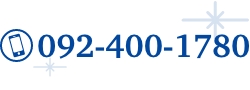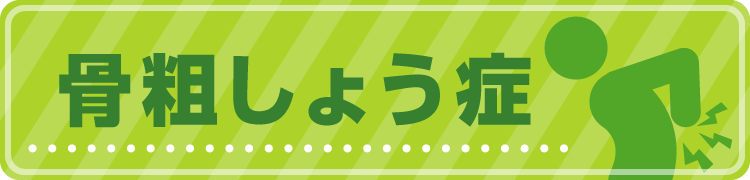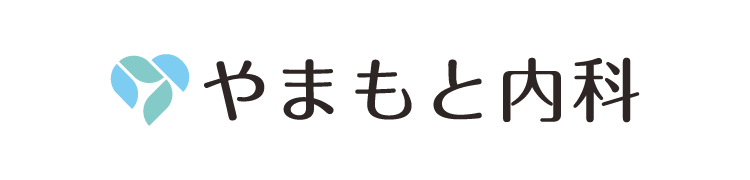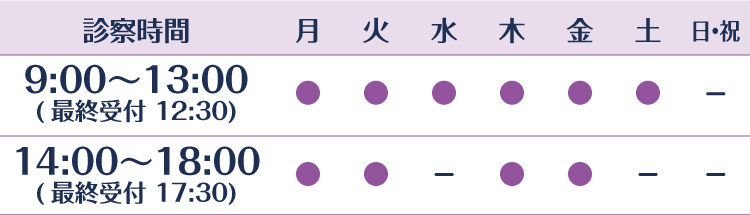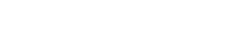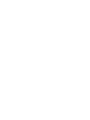福岡市西区の整形外科、リハビリテーション科「むらた整形外科」
診療案内
整形外科
整形外科で取り扱うのは手足、背骨からの原因で起こる症状(痛み、しびれ、筋力低下、動きの固さ、不安定感など)です。
関節、骨、脊椎、末梢神経、筋肉などの疾患から、すり傷、切り傷、骨折、脱臼、捻挫などのケガまで幅広く診療しています。
病院にかかろうと思っても、どの科を受診していいか迷っている方も多いかと思います。
関節、骨、脊椎、末梢神経、筋肉などの疾患から、すり傷、切り傷、骨折、脱臼、捻挫などのケガまで幅広く診療しています。
病院にかかろうと思っても、どの科を受診していいか迷っている方も多いかと思います。

以下のような症状がある方は、整形外科に相談してみてください
肩
肩を挙げる時の痛み、寝ているときの肩の痛み
- 肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)
- 腱板損傷
- 石灰沈着性肩関節炎
思春期のボールを投げる時の肩の痛み
- 野球肩
手をついた後より急に肩が痛くなり、動かなくなった
- 肩関節脱臼
股関節(足の付け根)
徐々に股関節が痛くなってきた
- 変形性股関節症
- 大腿骨頭壊死症
- 石灰沈着性股関節炎
3~10歳くらいの子供が急に股関節または膝を痛がり歩かなくなった
- 単純性股関節炎
- 化膿性股関節炎
- ペルテス病
転倒後より股関節が痛くなった
- 大腿骨頸部骨折
赤ちゃんの検診で股関節の異常を指摘された
- 先天性股関節脱臼
膝関節
徐々に膝が痛くなってきた、特に立ち上がりで痛い、膝が腫れている
- 変形性膝関節症
スポーツ時に膝を捻った後の膝痛
- 膝前(後)十字靭帯損傷
- 膝内側(外側)半月板損傷
膝のお皿を強打した後より歩行困難になった
- 膝蓋骨骨折
膝を曲げた後よりお皿の骨がずれて、膝を伸ばせなくなった
- 膝蓋骨脱臼
足首~足先
足首を捻った
- 足関節捻挫
- 足関節外果骨折等の骨折
徐々に足首の痛みが出て腫れもある
- 変形性足関節症
急に足首が痛くなって動かせなくなり、また全く痛くなるということを繰り返す
- 足関節内遊離体(関節ねずみ)
足首~足先のどこかの関節(特に足の親指の付け根)に急に激痛がでて赤く腫れる
- 痛風
足の親指が外側(小指側)に向いて変形してきている
- 外反母趾
頚部
首から背中、肩に痛み(肩こり)があり、良かったり悪かったりを繰り返している
- 変形性頚椎症
- 頚肩腕症候群
- 頚椎捻挫
首の痛みと腕~手に続く痛みしびれがある
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 頚椎症性神経根症
- 頚椎症性脊髄症
腰背部
急に腰痛が出て動けなくなった
- 急性腰痛症
【症状・病態】
一般的には、1番下の肋骨からお尻までの間に起きる痛みのことを腰痛と言います。
その症状のうち、発症して4週未満のものを急性腰痛と言います。
よく知られているものであれば、ぎっくり腰がこの中に含まれます。
筋肉や椎間板、椎間関節、仙腸関節に炎症が起きていると考えられていますが、画像検査で写らないこともあり、実際には完全には原因が解明されていません。
椎間関節由来の痛みがあるぎっくり腰は海外では魔女の一撃(witch’s shot)と言われるほど激しい痛みがあります。
【原因】
重たい物を持ち上げたり、腰を捻ったり、仕事で腰に負担をかけた際に起こるが多いですが、何もしなくても起きることもあります。
【検査】
診察、腰椎レントゲン、腰椎MRIなどで、腰椎に異常がないか調べます。また、骨、椎間関節、椎間板の評価を行います。
他の原因が隠れていないかさらに詳しい検査をすることもあります。
【治療】
治療としては消炎鎮痛薬の処方や神経ブロックなどがあります。
痛みが強い場合には安静としますが、必要以上な安静は逆効果です。
安静よりも活動維持をすることが大切であるため、痛みがない範囲での早期の活動再開を推奨します。通常では1カ月以内に痛みが軽快するものが多いです。
また、痛みが落ち着いてきたら、筋肉の硬さをほぐすことを目的にリハビリテーションを開始していきます。
腰部~臀部~太ももの裏の痛みしびれ(ふくらはぎまで続くこともあり)
- 腰椎椎間板ヘルニア
【症状・病態】
背骨と背骨の間には、クッションの役割を持つ椎間板があります。この椎間板が飛び出す事で神経を圧迫・刺激し症状をだします。
腰の神経を圧迫するため、圧迫を受けている場所で異なる腰・お尻・太ももやふくらはぎのしびれや痛み、麻痺症状を生じます。
前屈みになることで症状が増悪することが多く、場合によっては排便困難・排尿困難(膀胱直腸障害)を起こすことがあります。
【原因】
腰部に負担をかけやすい姿勢や動作、加齢・喫煙・遺伝的要因が原因になると言われています。
【検査】
診察時の所見、レントゲン画像、CT、MRIを用い総合的に判断します。
【治療】
基本的にはヘルニアになった人は自然に症状が軽快することが多い為、保存療法が主体になります。
保存療法では、初期に消炎鎮痛薬や神経の痛みを抑える薬を服薬しつつ、コルセットを装着して安静を促します。痛みが強い場合には、ブロック注射を行います。
また、日常生活が送れないほどの痛みが続いたり、明らかな下肢の麻痺や排尿・排便障害を認める場合には手術療法が選択される事があります。
また、日常生活が送れないほどの痛みが続いたり、明らかな下肢の麻痺や排尿・排便障害を認める場合には手術療法が選択される事があります。
長く歩いていると臀部~ふともも、ふくらはぎがしびれて途中で座って休憩してしまう、休憩するとまた歩けるようになる
- 腰部脊柱管狭窄症
【症状・病態】
症状としては歩いているとお尻~太もも、ふくらはぎのあたりに痛みやしびれ脱力が起きます。長時間歩くと、これらの症状が出現し座って休憩するとすぐ軽快するというのが代表的な症状です。そして体を反ると症状がひどくなる場合が多いです。歩いている時に下半身に痛みが出た場合は、その場で腰を丸めて休憩すると軽快する場合が多いので試してみてください。症状が酷い場合、排尿・排便困難などの膀胱直腸の症状が出ることもあります。
【原因】
加齢による背骨の変形により、神経の通る管が狭くなって神経を圧迫し神経症状が出現します。外傷性のものや先天性で生まれつき狭窄症になりやすい場合もあるので原因は様々です。
【検査】
診察での所見、X線、CT、MRIを用いて検査します。
【治療】
治療としてはお薬の処方、ブロック注射やリハビリでの筋力強化や生活指導等を行います。症状が酷く膀胱直腸の症状がある場合は手術が必要な場合が多いです。
尻もちをついたあと(もしくは腰に負担がかかることをしたあと)に、寝返り起き上がりのときの腰痛がある
- 腰椎椎体骨折(圧迫骨折)
【症状・病態】
背骨に圧力がかかることで、背骨が変形したり潰れて骨折した状態です。
主な症状としては、寝返り時の痛み、起き上がり時の痛み、体を動かした時の痛みがあります。初期では安静にしている時や歩く時は比較的痛みを感じにくいため、すぐに気が付かないことも少なくありません。
【原因】
大きく分けて2つの原因があります。
1つ目は、骨粗鬆症等により骨密度が低下していることです。その場合、”尻もちをついた”、”重いものを持った”など、腰に負荷がかかることで骨折してしまいます。
2つ目は、交通事故や転落事故などの強い外力が加わった外傷です。
【検査】
レントゲン検査、診察にて評価します。必要に応じてMRI検査や、骨粗鬆症が原因と疑われる場合は骨密度検査を行うこともあります。
【治療】
患者様お一人お一人に合わせてコルセットを作成します。
また、痛みが強い場合は消炎鎮痛薬を処方します。
背骨がゆがんでいる、学校検診で背骨の異常を指摘された
- 特発性側弯症
肘
物を持ち上げる時に肘の外側が痛い
- テニス肘
野球をしている小学生~高校生の肘の痛み
- 野球肘
肘の曲げ伸ばしが固い
- 変形性肘関節症
手首
手首の小指側が痛い(特にドアノブ動作で)
- TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)
【症状・病態】
手首の小指側が痛みます。
手をついたり、手首をひねる動作、特に「ペットボトルのキャップを開ける」「ふきんを絞る」「ドアノブを回す」「子供をだっこする」などの動作で痛みが出ることが多いですが、何もしていない時も痛む場合もあります。
【原因】
手首の小指側にある靭帯や腱、骨の周りにある軟骨などの軟部組織のまとまりのことをTFCC(三角線維軟骨複合体)といいます。
このTFCCがダメージを受けると、炎症が起きたり部分的に損傷したりすることで痛みがでます。
ダメージの原因として、スポーツや仕事で手首に負担がかかる動作を繰り返す、転んで手をつく、交通事故で手首に強い力がかかるなどがあります。また、思い当たる要因がなくてもTFCC損傷を起こす場合があります。
さらに、『尺骨突き上げ症候群』と呼ばれる状態になっている方もTFCC損傷の原因となります。
【検査】
レントゲン写真で手首の骨の状態をみます。
さらに詳しい画像検査が必要な場合にはMRI 撮影をします。
さらに詳しい画像検査が必要な場合にはMRI 撮影をします。
【治療】
まずは症状が落ち着くまで安静にすることが大切です。
この場合は手首を固定できるサポーターをつけていただくことがほとんどですが、当院では患者様の症状や生活スタイルによって、作業療法士が患者様それぞれの手首の形に合わせて固定用の装具を作ることが可能です。
サポーターや装具で安静を保ちつつ、痛みの強さに合わせて消炎鎮痛薬や炎症を抑える注射を使いながら経過をみていきます。
一定期間安静にしても症状が良くならない場合や、痛みが強く日常生活に支障が出てしまう場合には手術も選択肢の一つに挙がります。
手術を希望された方は、手術可能な病院で院長が手術をすることも可能です。
- 尺骨突き上げ症候群
【症状・病態】
外傷によってまたは外傷がないのに、『手を着くと小指側の手首が痛い』『ドアノブを回す動作や雑巾を絞る動作をすると痛い』といった小指側の手首の痛みが主症状です。
手首の骨と腕の骨がぶつかる事で骨の表面を覆う軟骨を痛めたり、関節に炎症が起こります。
手首の骨と腕の骨がぶつかる事で骨の表面を覆う軟骨を痛めたり、関節に炎症が起こります。
【原因】
手根骨(手の甲の骨)と尺骨(腕の骨)がぶつかる事で痛みが出ます。
通常は腕にある2本の骨(橈骨・尺骨)は手首の位置で同じ長さになっているのですが、生まれつきや外傷による影響で小指側の骨(尺骨)が少し長くなる場合があります。その為、手首にある骨とぶつかってしまい痛みが出現します。
通常は腕にある2本の骨(橈骨・尺骨)は手首の位置で同じ長さになっているのですが、生まれつきや外傷による影響で小指側の骨(尺骨)が少し長くなる場合があります。その為、手首にある骨とぶつかってしまい痛みが出現します。
【検査・診断】
主にレントゲン検査で腕の骨(橈骨・尺骨)と手首の骨のバランスを確認します。また手首を動かして痛みを誘発する検査(ストレステスト)を実施して診断します。
さらに詳しく検査する場合はMRI、CTを用いて検査します。
さらに詳しく検査する場合はMRI、CTを用いて検査します。
【治療】
サポーターや装具などで固定する方法があります。安静にする事で炎症を抑えるのが目的です。
当院では症状や生活スタイルに合わせて作業療法士が固定用の装具を製作します。必要であれば消炎鎮痛剤などの内服といった対処療法が行われます。
安静にしていても症状に変化がない場合や仕事や日常生活に支障が出てしまう場合は手術という選択肢もあります。手術可能な病院で院長が執刀しますのでご相談ください。
当院では症状や生活スタイルに合わせて作業療法士が固定用の装具を製作します。必要であれば消炎鎮痛剤などの内服といった対処療法が行われます。
安静にしていても症状に変化がない場合や仕事や日常生活に支障が出てしまう場合は手術という選択肢もあります。手術可能な病院で院長が執刀しますのでご相談ください。
手首の付け根が痛い、腫れや熱を持っている
- 橈骨遠位端骨折
【症状・病態】
前腕(肘から手首までの部分)には2本の骨があり、そのうちの親指側の太い骨を橈骨といいます。この橈骨が手首の部分で折れることを橈骨遠位端骨折と呼びます。外力が加わった際に、手首に強い痛みや腫れ・変形などの症状がみられます。ときに、折れた骨や腫れによって神経が障害され、指に痺れが出たり感覚が鈍くなることもあります。
橈骨遠位端骨折は、怪我をした時の姿勢や折れた骨のズレる方向によって、コーレス型(折れた骨が手の甲側にズレた骨折)とスミス型(折れた骨が手の平側にズレた骨折)に大別されます。コーレス型は、橈骨遠位端骨折の中で最も多い骨折の種類です。また、橈骨遠位端骨折の合併症として手根管症候群・長母指伸筋腱断裂・複合性局所疼痛症候群(CRPS)などがあります。
橈骨遠位端骨折は、怪我をした時の姿勢や折れた骨のズレる方向によって、コーレス型(折れた骨が手の甲側にズレた骨折)とスミス型(折れた骨が手の平側にズレた骨折)に大別されます。コーレス型は、橈骨遠位端骨折の中で最も多い骨折の種類です。また、橈骨遠位端骨折の合併症として手根管症候群・長母指伸筋腱断裂・複合性局所疼痛症候群(CRPS)などがあります。
【原因】
多くは骨粗しょう症を有する中高年者が、転倒して手をついた場合に起こります。骨粗しょう症の方は骨が脆くなっているため、簡単に折れてしまいます。若年者でも、高所からの転落や交通事故・スポーツ中の事故など、強い外力が生じると起きてしまいます。橈骨遠位端骨折は、骨折のなかで頻度の高いものの一つであり、脊椎圧迫骨折・上腕骨近位部骨折・大腿骨近位部骨折などの骨粗しょう症を基盤とする、高齢者四大骨折の中の一つです。
【検査】
骨折の存在はレントゲンで診断します。
さらに詳しく判断するには、CTやMRIを撮影することもあります。
さらに詳しく判断するには、CTやMRIを撮影することもあります。
【治療】
橈骨遠位端骨折では、骨折の安定性や年齢によって治療法の適応が異なります。
安定型骨折(ズレが少なく安定している場合)では、徒手整復やギプス固定などの保存療法が適応となります。不安定型骨折(骨折した骨が大きくズレている場合)では、プレート固定などの手術療法が適応となることがあります。また痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤の内服などの対処療法が行われます。
安定型骨折(ズレが少なく安定している場合)では、徒手整復やギプス固定などの保存療法が適応となります。不安定型骨折(骨折した骨が大きくズレている場合)では、プレート固定などの手術療法が適応となることがあります。また痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤の内服などの対処療法が行われます。
親指を使うときに手首の親指側が痛い
- ドケルバン腱鞘炎
手をついたときに手首の甲側が痛い
- 手関節背側ガングリオン
手指
箸が使いにくい、シャツのボタンをとめにくい
- 手根管症候群
【症状・病態】
手を支配する神経は、正中神経・尺骨神経・橈骨神経の3本に分けられます。手根管症候群では、正中神経が手首の掌側にある手根管と呼ばれる骨性のトンネル部分で圧迫されることにより生じます。
症状は主に運動(指の動かしにくさ)と感覚(痛みやしびれ)の両方に生じます。
運動では特に親指の動きが悪くなり箸の使用やボタンかけなどの細かい作業が困難になると共に、親指の付け根の筋肉が痩せて”猿手”と呼ばれる変形をきたします。指でOKサインが作りにくくなるのが特徴です。
感覚では小指以外のしびれ・痛みを生じます。手首を振る事で症状が楽になる特徴があります。
症状は主に運動(指の動かしにくさ)と感覚(痛みやしびれ)の両方に生じます。
運動では特に親指の動きが悪くなり箸の使用やボタンかけなどの細かい作業が困難になると共に、親指の付け根の筋肉が痩せて”猿手”と呼ばれる変形をきたします。指でOKサインが作りにくくなるのが特徴です。
感覚では小指以外のしびれ・痛みを生じます。手首を振る事で症状が楽になる特徴があります。
【原因】
多くは原因不明と言われていますが、女性に多く発症します。
また、関節リウマチ、手首周囲の骨折、透析、指の腱鞘炎などの病気をもつ場合や、妊娠・閉経などの女性ホルモンの影響でも発症リスクが高まります。病気や体調の変化以外にも、単純に重労働で手を過度に使用しやすい方などにも発症しやすいと言われています。
また、関節リウマチ、手首周囲の骨折、透析、指の腱鞘炎などの病気をもつ場合や、妊娠・閉経などの女性ホルモンの影響でも発症リスクが高まります。病気や体調の変化以外にも、単純に重労働で手を過度に使用しやすい方などにも発症しやすいと言われています。
【検査・診断】
診察、レントゲン検査、神経伝導速度検査にて評価します。必要に応じてCT・MRI検査が追加されることもあります。
【治療】
指の動きにくさや痛み・しびれや感覚の低下などの症状が軽症の場合、まず保存療法が選択されます。保存療法では手首の安静・手首の固定(装具を用います)・服薬・注射などの手段を用います。
症状が重症の場合は早い段階での手術が勧められています。
症状が重症の場合は早い段階での手術が勧められています。
- 頚椎症性脊髄症
中指、人差し指がしびれて痛む、感覚が弱い
- 手根管症候群
小指がしびれる、感覚が弱い(肘を曲げて手を使うときなど)
- 肘部管症候群
特に朝起きた時に指がカクンとひっかかる
- ばね指
急に(朝起きた時など)に手首や指がのばせなくなった
- 橈骨神経麻痺
朝の手指のこわばり
- 関節リウマチ
【症状・病態】
自己免疫疾患の一つです。自分の身体の細胞の一部を自分のものではないとして、これに対する抗体を作って反応をおこしてしまい、関節内に存在する滑膜(かつまく)という組織に炎症が起きます。滑膜から産生される破壊物質が、次第に自分の軟骨や骨を破壊していく病気です。
全身の関節の炎症によって手や、肩、膝、足などの関節が腫れて痛みがでます。朝の手のこわばりや、指の第二関節や付け根、手首に痛みがでることが多いです。症状が進行すると関節の変形や破壊により、関節を思うように曲げ伸ばしできない等の症状がでます。
関節リウマチは早期の治療が重要となります。少しでも気になる症状がある方や血縁者にリウマチの方がいらっしゃる際はご相談ください。
【原因】
遺伝や環境、細菌・ウイルス感染によって自己免疫の異常が起こると考えられていますが、原因はよくわかっていません。
【検査】
レントゲン検査、エコー検査、血液検査を行います。
【治療】
抗リウマチ薬やステロイドの内服治療、生物学的製剤を使用した注射治療などがあります。
薬剤を使用することでリウマチによる炎症を抑え、関節を壊していくことを抑えていきます。腫れや痛みが強い場合は、症状がある部分にステロイド注射を打つこともあります。また、症状に合わせた漢方薬を処方することもあります。
運動療法や作業療法で症状を予防・改善していきます。
関節の変形が進行したり、日常生活でお困りの場合は手術になることもあります。
- ばね指
手指の関節の痛み、腫れ
- 関節リウマチ
- へバーデン結節
- ブシャール結節
親指の付け根が痛む
- 母指CM関節症
手の甲の筋肉がやせてきた
- 肘部管症候群
- 平山氏病
手の指の関節が固くて動かない
- 手指関節拘縮
指の爪が痛む(特に寒いとき)
- グロムス腫瘍
リハビリテーション科
全身の痛みやしびれ、動かしづらさでお悩みの方に、理学療法士による運動療法と物理療法を組み合わせ、予防に力を入れたリハビリを行っていただきます。お一人お一人の症状に合わせて、医師とリハビリスタッフがリハビリプランをご提案し、症状改善に向けた体づくりをサポートいたします。まずはご相談ください。
骨粗しょう症
骨粗しょう症になると、尻餅をつく、手をつく、重いものを持つ、草抜きをするなどささいなきっかけで骨折してしまいます。進行すると子犬を抱っこしただけで背骨が折れたり、中にはきっかけさえ分からない「いつの間にか骨折」を起こす可能性もあります。当院ではDEXA法という正確な骨密度測定を行い診断し、治療をしています。
当院で行う手術について
手術が必要と診断し、患者様が手術を希望された場合には、当院または連携病院にて院長自らが手術を行います。
手術後も当院で治療やリハビリテーションを行っていただき、患者様が元気に回復していただけるまでサポートいたします。
手術後も当院で治療やリハビリテーションを行っていただき、患者様が元気に回復していただけるまでサポートいたします。
手術についてのQ&A
- どんな時に手術になるのですか?
- 基本的にはまず手術以外の治療(保存治療)を行います。
ただし手術をしないと後遺症が残ったり、症状が徐々に進行すると考えられる場合に手術をすすめさせていただいてます。
- どのような疾患に対し手術を行っているのですか?
- 主に肘~手指に対する手術を行っております。具体的にはばね指、手根管症候群、軟部腫瘍、ガングリオン、靭帯断裂、腱断裂、テニス肘、伸筋腱脱臼、滑膜炎、関節拘縮などです。
- 手術は痛いですか?
- 適切な麻酔を行いますので、手術中に痛むことはありません。
- どのような麻酔をしているのですか?
-
手術によりこれらの麻酔を使い分けております。
- 患部周辺に直接麻酔薬を注射する局所麻酔
- 指の根本に麻酔薬を注射し指1本を麻酔する指ブロック麻酔
- エコーを用いて脇から麻酔薬を注射して腕1本を麻酔する腋窩麻酔
- 手術はどこで行っているのですか?
- 日帰り手術は当院で行っております。もし入院が必要な場合は、入院施設のある連携病院の手術室を予約して、そこで院長が手術を行っております。
- 手術はいつ行っているのですか?
- 基本的には外来診療のない水曜日の午後に手術を行っております。それは当院で行う場合も、連携病院で行う場合も同じです。
- 診断から手術までの流れを教えてください。
- 手術が必要と診断され、手術を希望された場合はまず手術日を決定します。手術日の約1週間前に術前検査(採血、胸写、心電図等)、医師からの手術説明、看護師からの案内をさせていただきます。診断日と手術日が近い場合は診断日に術前検査等を行うこともあります。
- 手術日の流れを教えてください。
-
- 指定時間に来院後、会計(預り金のみ)をしていただきます。
- 点滴などの準備が整い次第手術台に寝ていただきます。
- 麻酔後、術野(手術をするところ)が消毒され、無菌のシーツで囲われます。それにより患者様から術野は見えなくなります。
- 手術を終え体調に問題がなければ手術後の説明を受け、処方箋をうけとり帰院していただきます。
- 手術後は痛いですか?
- 局所麻酔、指ブロック麻酔の場合は麻酔後1時間ほどで、腋窩麻酔の場合は麻酔後4時間~12時間ほどで麻酔が切れます。術後に痛み止めの薬を処方しますので、それで対処していただきます。
- 手術後の流れは?
- 手術翌日(場合によっては手術翌々日)に再来していただきます。創処置を行ったあと、その日の会計時に手術の残りの会計も併せて行っていただきます。その後抜糸までは数日に1回の創処置を行います。
- 抜糸までの期間は?
- 術式によりますが術後10~14日ほどで抜糸になります。
- 術後は入浴できるのですか?
- 抜糸までは患部が濡れたり蒸れたりしないように注意しての入浴は可能です。ただし術式によってはシャワー浴にしていただくこともあります。
- 手術時間はどのくらいですか?
- 術式によりますが手術時間は10~45分ほどです。麻酔を含めた前後の時間を含めると手術室滞在時間は30~90分ほどになります。
- 手術日は運転して帰ってもいいのですか?
- 麻酔が効いており危険なので控えていただいています。
- 付き添いは必要ですか?
- 20歳以上の方であれば必要ありませんが、説明を希望される方は来ていただいても構いません。
当院での漢方薬治療について
当院では患者様の症状によっては漢方薬を処方しています。全疾患に対して処方をしているわけではありませんが、当院の大きな武器として有効活用しています。
改善が乏しい症状、筋肉が硬かったり攣りやすいなどの症状、体質改善を目的とする場合(冷え性やむくみ等)などに使用していきます。
漢方薬は副作用が少ないお薬ですので、慢性的に消炎鎮痛薬を内服し消化器症状がでている方や副作用が怖くてお薬を内服することに抵抗がある方、または妊娠・授乳中の患者様にも処方することができます。
漢方薬は1日3回内服の粉末タイプが多いですが、種類によっては1日2回内服や錠剤の漢方薬もあり、患者様のニーズに合わせた処方もできます。
下記の該当症状がある際はお気軽にご相談ください。
改善が乏しい症状、筋肉が硬かったり攣りやすいなどの症状、体質改善を目的とする場合(冷え性やむくみ等)などに使用していきます。
漢方薬は副作用が少ないお薬ですので、慢性的に消炎鎮痛薬を内服し消化器症状がでている方や副作用が怖くてお薬を内服することに抵抗がある方、または妊娠・授乳中の患者様にも処方することができます。
漢方薬は1日3回内服の粉末タイプが多いですが、種類によっては1日2回内服や錠剤の漢方薬もあり、患者様のニーズに合わせた処方もできます。
下記の該当症状がある際はお気軽にご相談ください。
◇芍薬甘草湯
よく足が攣(つ)る、攣りを予防したい 筋肉を和らげたい
◇防已黄耆湯
膝に水が溜まっている
◇越婢加朮湯
膝に水が溜まっている 関節が痛く、赤く熱感がある
◇二朮湯
よく足が攣(つ)る、攣りを予防したい 筋肉を和らげたい
◇芍薬甘草湯
肩の関節が痛い
◇葛根湯
肩が凝っている
◇葛根加朮附湯
肩が凝っている 体が冷えている
◇五苓散
手の指を曲げるとひっかかる、浮腫んでいる 天気が悪いと頭痛がする
◇柴苓湯
手の指を曲げるとひっかかる 関節が腫れて痛い
◇牛車腎気丸
腰が痛い、下肢が痛い
◇八味地黄丸
腰が痛い、疲れやすい
◇よく苡仁
朝起きて足をつくときに足の裏が痛い
◇桂枝茯苓丸
指の関節が痛い
◇加味逍遙散
指の関節が痛い 更年期症状がある
◇桂枝加朮附湯
関節が痛く、冷えると悪化する
◇疎経活血湯
腰が痛い 冷えると痛みが増強する
◇治打撲一方
打撲して内出血がある
◇補中益気湯
食欲がない、夏バテする
◇人参養栄湯
食欲がない
◇半夏白朮天麻湯
めまいがする